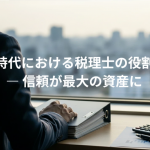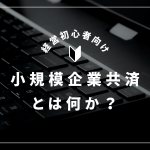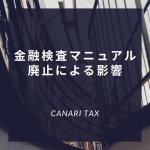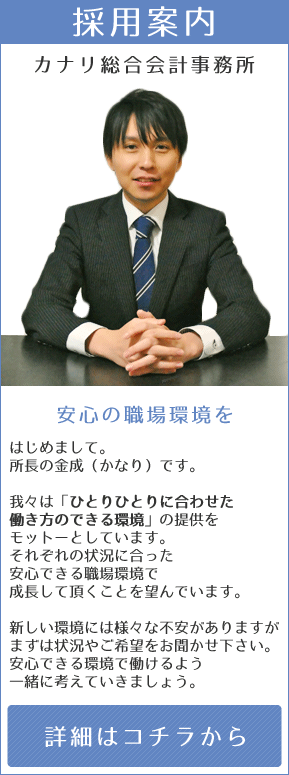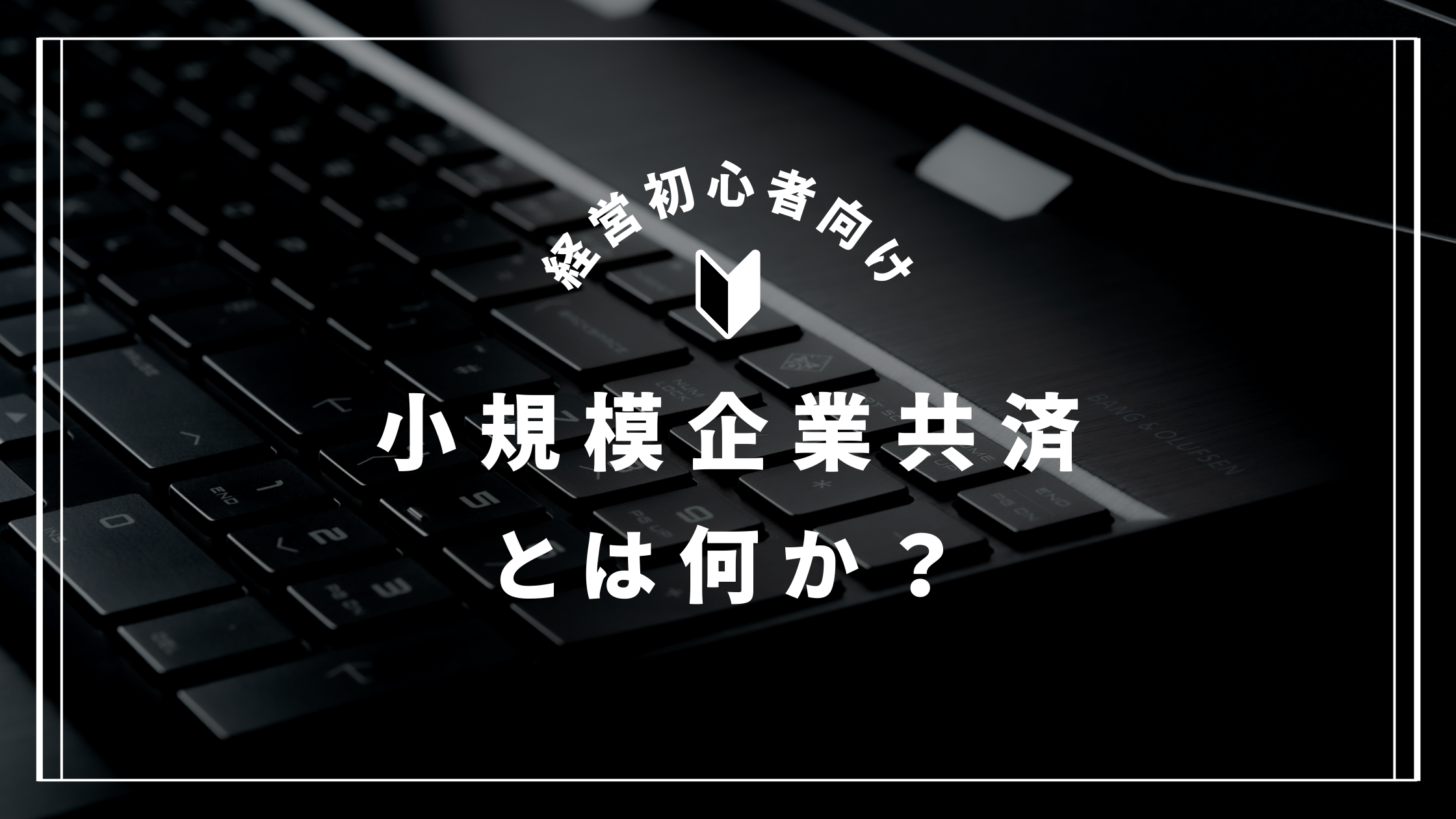
Contents
小規模企業共済とは何か?―制度の仕組みと節税効果、法人活用の実務まで徹底解説(2025年8月時点)
中小企業の経営者や個人事業主にとって、老後資金や退職金の準備は喫緊の課題です。
そんな中、節税効果も期待できる「小規模企業共済」は、多くの方にとって有効な選択肢となり得ます。
本記事では、制度の概要から税務上の扱い、さらには法人における“実質的な損金化”の方法まで、2025年8月時点の最新情報をもとに詳しく解説します。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、【中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)】が運営する共済制度です。中小企業の経営者や役員、個人事業主が、廃業や退職後に備えて積み立てを行う「経営者のための退職金制度」として位置づけられています。
-
運営主体: 中小機構(公式サイト)
-
加入者数: 約160万人(2022年時点)
加入資格
加入できるのは、以下のような一定規模以下の事業を営む個人または法人の役員です。
| 業種 | 常時使用する従業員数の上限 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業など | 20人以下 |
| 小売業・サービス業など | 5人以下 |
詳しくは中小機構の「加入資格の詳細」をご確認ください。
掛金と給付のしくみ
-
掛金: 月1,000円〜7万円の範囲で500円単位で設定可。途中で増減も可能(ただし減額には制限あり)。
-
支払方法: 月払い・半年払い・年払い・前納の選択が可能。
-
共済金: 以下の種類があります。
| 共済金の種類 | 支給要件 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 共済金A | 廃業・退職・死亡 | 退職所得 |
| 共済金B | 65歳以上かつ掛金180ヶ月以上 | 退職所得または雑所得(分割) |
| 準共済金 | 法人成りなどによる加入資格喪失 | 退職所得 |
| 解約手当金 | 任意解約など | 一時所得(必要経費控除不可) |
詳細な受給条件については共済金の受給要件をご参照ください。
掛金の税務上の取扱い
掛金の全額が所得控除に
小規模企業共済に支払った掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除されます(所得税法第69条)。
これは、給与所得控除や社会保険料控除などと並び、個人にとって非常に強力な節税手段です。
-
上限: 年間84万円(月額7万円×12ヶ月)
-
控除対象者: 契約者本人のみ(法人では不可)
-
手続き: 確定申告または年末調整で、中小機構が発行する「掛金払込証明書」を提出
詳しくは国税庁の小規模企業共済等掛金控除についてをご確認ください。
解約・受取時の税務(事由別)
| 解約・支給事由 | 課税区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 廃業・退職・死亡 | 退職所得 | 勤続年数に応じた退職所得控除あり。1/2課税。 |
| 65歳以上での解約 | 原則退職所得 | 事業継続中でも対象。 |
| 法人成りによる資格喪失(準共済金) | 退職所得 | 実質的に「事業主としての退職」と見なされる。 |
| 任意解約(65歳未満) | 一時所得 | 掛金は必要経費とならず、元本割れもあり得る。 |
| 死亡による共済金 | 相続税の課税対象 | 相続人ごとに500万円の非課税枠あり(相続税法施行令第3条1項5号)。 |
法人で損金化するには?役員報酬上乗せの活用
小規模企業共済はあくまで個人契約であるため、法人が掛金を負担しても損金にはなりません。しかし、実務上は次のようにして法人が実質的に負担しつつ、損金算入を実現する方法があります。
方法:役員報酬への上乗せ
-
掛金額と同額を毎月の役員報酬に上乗せする。
-
その分を役員個人が共済掛金として支払う。
メリット
-
法人:上乗せ分は損金(人件費)となり、法人税が減る。
-
個人:給与は増えるが、同額が控除されるため所得税・住民税は増えない。
-
双方にとって節税メリットがある。
実例シミュレーション
-
掛金:月3万円 → 年36万円
-
法人税実効税率30%と仮定 → 法人税約10.8万円軽減
-
個人の手取り影響:なし(控除で相殺)
実施時の注意点
-
定期同額給与の原則: 事業年度開始後3ヶ月以内に報酬額を変更し、以降は毎月同額で支給。
-
手続き: 株主総会または取締役会での決議(議事録必須)。
-
会計処理: 増額分は通常の「役員報酬」として仕訳。
-
社会保険料の増加: 給与増に伴う保険料負担増を考慮。
参考:国税庁「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
解約リスクと対策
小規模企業共済には一定のリスクもあります。たとえば、掛金納付期間が短いうちに解約した場合には元本割れが生じます。
-
12ヶ月未満で任意解約:掛金は戻らない
-
20年未満:元本割れの可能性
-
20年以上:元本超え(解約手当金が掛金総額以上)
解約回避の工夫:契約者貸付制度の活用
急な資金需要が生じた場合は、共済契約を維持したまま【契約者貸付制度】を活用することも可能です。
-
融資限度:掛金納付総額の7〜9割程度
-
金利:年利1.5%程度(変動あり)
-
詳細:中小機構「契約者貸付制度」
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/loan/index.html